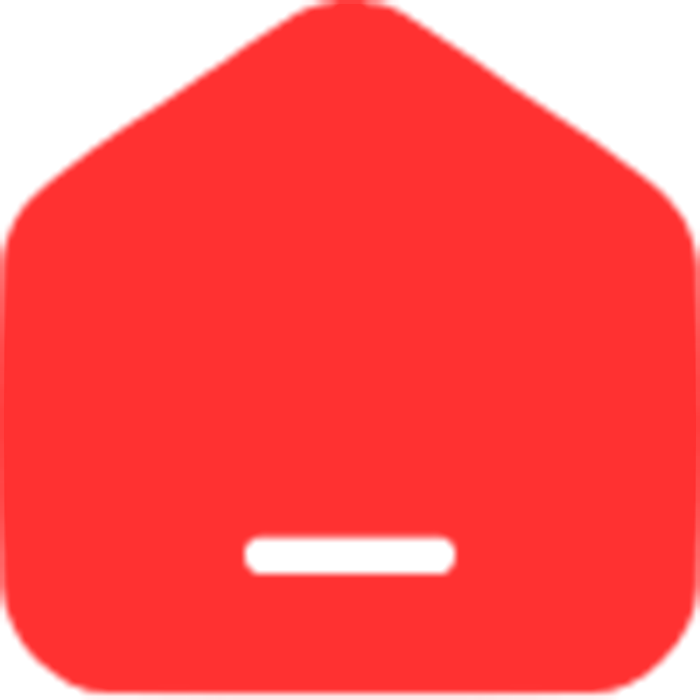【2025年版】リフォーム減税制度の種類や条件、確定申告について解説

リフォーム減税とは、一戸建てやマンションのリフォームを行った際に、税の控除や減額を受けられる制度です。
耐震や介護、省エネなど、減税対象となるリフォーム工事はさまざまあります。
2025年(令和7年)度のリフォーム減税制度について、工事内容や条件、申請方法まで詳しく解説するので、ぜひ快適なリフォームを実現する参考にしてください。
目次
2025年(令和7年)もリフォーム減税制度は使える?
リフォーム減税は、主に所得税・固定資産税が対象となり、控除・減額を受けることができる制度です。
2025年(令和7年)度も引き続きリフォーム減税制度が利用できます。
適用期間は、2025年12月31日まで!
また、2024年度の税制改正にて適用されていた「子育て世帯に対する住宅ローン減税の特例措置※工事費用の10%(最大25万円)が所得税から控除」も2025年12月31日まで延長になっています。
リフォーム減税できる税金の種類
リフォーム減税できる税金の種類は以下の通りです。
| ・所得税 ・固定資産税 ・贈与税 ・不動産取得税 ・登録免許税 |
ほとんどが、所得税・固定資産税の対象になりますが、条件によっては贈与税や不動産取得税、登録免許税の軽減対象になる可能性があります。
リフォーム減税の対象工事一覧
次に、減税の対象工事一覧です。
それぞれの工事が、どの税金の控除または減額を受けられるかも確認しましょう。
| 耐震 | 所得税 固定資産税 贈与税 登録免許税 不動産取得税 |
| バリアフリー | 所得税 固定資産税 贈与税 登録免許税 不動産取得税 |
| 省エネ | 所得税 固定資産税 贈与税 登録免許税 不動産取得税 |
| 同居対応 | 所得税贈与税(※工事内容による) 登録免許税(※工事内容による) 不動産取得税(※工事内容による) |
| 長期優良住宅化 | 所得税固定資産税贈与税(※工事内容による) 登録免許税(※工事内容による) 不動産取得税(※工事内容による) |
| 子育て対応 | 所得税 |
| その他(増改築) | 所得税 贈与税 登録免許税 不動産取得税 |
耐震・バリアフリー・省エネリフォームは、要件を満たせば5種類の税金を減額(控除)することが可能です。
一方、同居対応・長期優良住宅化は、工事内容によって大きく変わります。
子育て対応は、所得税が対象なのに対して、その他(増改築)は4種類の減税対象のため、うまく利用してお得に施工プランを立てましょう。
リフォーム減税の条件|所得税

まずは、所得税の減税対象のリフォームについて解説します。
限度額や控除率、期間など詳しくみていきましょう。
耐震リフォーム
耐震リフォームは、リフォーム促進税制の1つです。
ローンの有無に関係なく、耐震基準に適合するよう住宅を改修した場合に、所得税の控除を受けられます。
| 工事内容 | 耐震基準に適合する耐震改修 |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円(工事限度額250万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・1981年5月31日以前に建築された住宅リフォーム ・耐震改修工事が2025年12月31日までに完了 ・合計所得金額が2,000万円以下 …など他の条件もあり |
工事費用から補助金などの金額を引いた額が減税対象となります。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームを行った場合(対象者や工事内容に条件あり)、所得税の控除を受けられます。
たとえば「車椅子の利用により廊下を拡張」「介助のための手すり設置」などが対象になります。
| 工事内容 | バリアフリー改修 |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 20万円(工事限度額200万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・バリアフリー改修工事が2025年12月31日までに完了 ・合計所得金額が2,000万円以下 ・当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上 ・対象者の条件に当てはまる …など他の条件もあり |
| 対象者 | ・50歳以上 ・障害を持っている ・要介護認定または要支援認定を受けている ・障害を持つまたは要介護認定、要支援認定と同居している |
対象となるバリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事は以下の通りです。
- 通路の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床材料の取替え
省エネリフォーム
省エネリフォームは、住んでいる既存住宅に窓の断熱改修工事(必須)などが対象となり、所得税の減税が受けられます。
| 工事内容 | 省エネ改修 |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円(工事限度額250万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・窓の断熱改修工事を行っている ・耐震改修工事が2025年12月31日までに完了 ・当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上 …など他の条件もあり |
省エネ改修工事の内容は以下の通りです。
- 窓の断熱改修※必須
- 天井、壁、床の断熱改修
- 太陽熱利用冷温熱装置の設置
- 高効率給湯器の設置
- 高効率エアコンの設置
- 太陽光発電設備の設置
同居対応リフォーム
同居対応リフォームは、親・子・孫の世代間の助け合いがしやすい環境づくり・同居を前提に増築改修工事を対象としています。
| 工事内容 | 同居対応化改修 |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円(工事限度額250万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・改修後、調理室・浴室・便所・玄関いずれか2室以上複数ある ・耐震改修工事が2025年12月31日までに完了 ・当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上 ・家屋の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住 …など他の条件もあり |
同居対応改修工事の内容は以下の通りです。
- 調理室の増設
- 浴室の増設
- 便所の増設
- 玄関の増設
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームは、耐震リフォームまたは、省エネリフォームと併せて、耐久性向上改修を実施した場合、所得税の控除を受けられます。
| 工事内容 | 長期優良住宅化改修 |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円(工事限度額250万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・増改築による長期優良住宅の認定を受けている ・耐震改修工事が2025年12月31日までに完了 ・当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上 ・耐震基準に適合させる耐震改修または省エネ改修も行っている …など他の条件もあり |
耐久性向上改修(長期優良住宅化改修)・省エネ工事の内容については、木造・鉄筋・RCでそれぞれ異なるので確認しましょう。
子育て対応リフォーム
子育て対応リフォームは、子どもの事故を防止する改修や配慮したい改修など、子育てにまつわる工事が対象となります。
| 工事内容 | 子育て対応リフォーム |
| 控除期間 | 1年 |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円(工事限度額250万円) |
| 適用期間 | 2025年12月31日まで |
| 適用条件 | ・対象者が19歳未満の扶養親族を有している人、またはご自身 ・その配偶者のいずれかが40歳未満 ・耐震改修工事が2025年12月31日までに完了 ・当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上 ・耐震基準に適合させる耐震改修または省エネ改修も行っている …など他の条件もあり |
子育て対応リフォームは2024年末までの減税制度でしたが、2025年の税制改正大綱において1年の延長が決まりました。
2025年12月31日までに期限が延長が確定したものの、関係税制法が成立することが前提のため、期限後は最新の情報を確認することが大切です。
対象となる工事内容が細かく分類されているので、確認しましょう。
住宅ローン減税
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、住宅ローンで新築・中古住宅を購入した場合に利用できます。
さらに、リフォームの際に、住宅ローンやリフォームローンを組む場合でも利用できます。
| 控除期間 | 10年 |
| 借入限度額 | <3,000万円> ・長期優良住宅 ・ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅 <2,000万円> ・その他の住宅 |
| 控除率 | 0.7% (年末時点のローン残高×0.7%) |
| 最大控除額 | 140万円 |
| 適用期間 | 2025年12月まで |
| 適用条件 | ・対象の工事費用が100万円(税込)を超える ・所得金額の合計が2,000万円以下 ・住宅の床面積が50㎡以上 ・工事完了から6ヶ月以内に入居 …など他の条件もあり |
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除が適用されます。
リフォーム減税の条件|固定資産税

リフォームで所得税の控除だけではなく、固定資産税の減額ができるケースもあります。
- 耐震
- バリアフリー
- 省エネ
- 長期優良住宅化
減税期間は1年、工事完了後3ヶ月以内に申告、改修工事は2026年3月31日までに完了していることが必須です。
ただし、家屋面積の制限や他の減税と併用ができるものとできないものがあるため確認しましょう。
耐震リフォーム
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に適用されます。
| 工事内容 | 耐震改修 |
| 減額割合 | 固定資産税の2分の1 |
| 適用条件 | ・昭和57年1月1日以前から所在する家屋 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修 ・耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えている ・店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用 ・改修工事を令和8年3月31日までに行っている |
バリアフリーリフォーム
一定のバリアフリー改修工事を実施、また減額対象者の条件に適合する場合に、翌年度分の固定資産税から減額されます。
| 工事内容 | バリアフリー改修 |
| 減額割合 | 固定資産税の3分の1 |
| 適用条件 | ・新築されてから10年以上が経過した家屋 ・賃貸住宅ではない家屋 ・工事に要した費用から補助金を差し引いた額が、50万円(税込)を超えている ・改修後の床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用 ・改修工事を令和8年3月31日までに行っている |
| 対象者条件 | 以下のいずれかに該当する減税申請者が、居住している家屋である ①65歳以上の者 ※工事が完了した翌年の1月1日時点 ②要介護認定または、要支援認定を受けている者 ③障害を持っている者 |
国土交通省:バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置PDF
省エネリフォーム
熱損失防止改修工事や省エネ改修工事が対象になりますが、細かく分類されているので確認が必要です。
なお、上記の対象改修工事と併せて、窓の断熱改修工事は必須になります。
| 工事内容 | 省エネ改修 |
| 減額割合 | 固定資産税の3分の1 |
| 適用条件 | ・省エネ改修後の断熱部位が平成28年基準を新たに満たしている ・平成26年4月1日以前から所在している家屋 ・賃貸住宅でない家屋であること ・省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えている※工事個別の金額要件があるため、費用は要確認 ・床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用 ・改修工事を令和8年3月31日までに行っている |
長期優良住宅化リフォーム
耐震工事または、省エネ工事と併せて長期優良住宅の認定を受けると、固定資産税が減額されます。
長期優良住宅の認定には、インスペクション(住宅診断)の実施は必要になりますが、費用は補助金対象になっています。
| 工事内容 | 省エネ改修 |
| 減額割合 | 固定資産税の3分の1 |
| 適用条件 | ・増改築による長期優良住宅の認定を受けている ・床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用 ・改修工事を令和8年3月31日までに行っている |
| 適用条件<耐震改修工事> | ・昭和57年1月1日以前から所在する家屋 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修 ・耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えている |
| 適用条件<省エネ改修工事> | ・平成26年4月1日以前から所在する家屋 ・当該家屋が賃貸住宅ではない ・省エネ改修工事費から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えている※工事個別の金額要件があるため、費用は要確認 |
国土交通省:長期優良住宅化改修に係る固定資産税の減額措置PDF
リフォーム減税の条件|贈与税
両親や祖父母からリフォームに関わる資金援助を受けた場合も、条件を満たせば、贈与税が非課税になります。
| 期間 | 2024年1月1日~2026年12月31日 |
| 非課税限度額 | ・一般住宅:500万円 ・質の高い住宅:1,000万円 ※一定の要件あり (省エネ・耐震・バリアフリーなど) |
| 対象リフォーム | ・耐震 ・バリアフリー ・省エネ ・増改築 |
| 適用条件 | ・リフォーム後の家の床面積が50~240㎡ ・贈与を受ける方が、贈与者の子どもまたは、孫である ・贈与を受ける年の1月1日時点で、18歳以上 ・贈与を受ける年の収入が2,000万円以下 …など他の条件もあり |
リフォーム減税の条件|その他
一定の条件を満たした場合、「不動産取得税」「登録免許税」の軽減が受けられることがあります。
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる課税のことです。
ただし、取得後にリフォームを行うことで、4%から3%に減税できる可能性があります。
条件は以下の通りです。
<不動産取得税の減税条件>
- 1981年12月31日以前に新築された住宅
- 取得後6ヶ月以内に耐震改修工事を実施
- 耐震基準適合証明書を取得
…など
登録免許税とは、住宅の所有を法務局の登記簿に記録する手続きを登記といい、このときにかかる税金を指します。
住宅性能向上リフォームの改修工事が実施された住宅を購入・居住すると、所有権移転登記に対する登録免許税の税率が0.3%から0.1%に軽減されます。
登録免許税の減税にも条件があり、以下の通りです。
<登録免許税の減税条件>
- 対象となる工事費用の総額が300万円
- または、家屋の譲渡対価の20%以上に相当する
- 工事費用が一定の水準を満たしている
…など
リフォーム減税制度の申請方法と必要書類
自動的に税金は減額してくれないので、必ず期日までに申請をしましょう。
所得税・贈与税は、『税務署にて確定申告』です。
一方、固定資産税は、『市区町村にて手続き』となります。
それぞれ、必要となる書類が異なるのでここでは、耐震リフォームを参考に紹介します。
| <所得税・贈与税の申請書類> ・確定申告書 ・住宅特定改修特別税額控除の計算明細書 ・増改築等工事証明書 ・住宅耐震改修証明書 ・工事完了後の家屋の登記事項証明書 ・補助金等の額が明らかな書類 ・源泉徴収票 …など | <固定資産税の申請書類> ・固定資産税減額申告書 ・耐震リフォームの費用の額が確認できる書類 (耐震改修費用が50万円超であることを証明する書類) ・増改築等工事証明書(発行者の建築士の免許証の写し又は免許証明書を添付) ・住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が証明する場合) ・リフォーム後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合に限る) …など |
ほとんどの工事が申請時に必要となるのが「増改等工事証明書」です。
こちらは、建築士が在籍している施工会社でしか原則発行できないので注意しましょう。
また、工事内容の証明書や施工写真、領収書の提出が必要になったり、補助金制度を利用した場合は金額がわかる書類が必要になったりするので、あらゆるものを大切に保管するようにしてください。
まとめ
2025年に適用されるリフォーム減税制度について紹介しました。
どの制度も毎年当たり前に受けられるとは限りません。
必ずリフォームを実施する年に、どんな制度が設けられているのか確認しましょう。
制度それぞれに、適用条件や必要書類があり、申請が難しい…と感じる人もいるかと思います。
申請はご自身で行う必要がありますが、基本的にリフォーム会社(施工会社)と相談しながら準備できるのでご安心ください。
リフォーム費用は決してお安いものではないため、上手に制度を利用してお得に快適なマイホームつくりをしましょう!