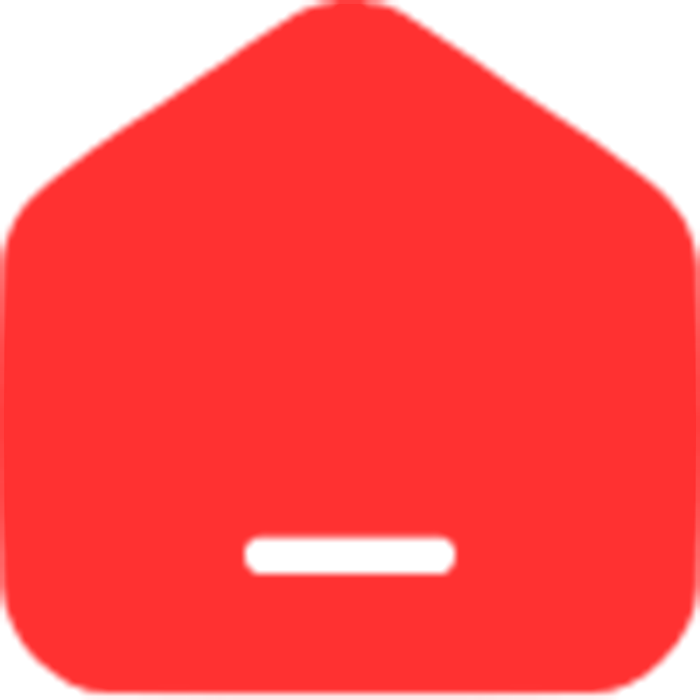耐震補強は意味がない?耐震リフォームの費用や補助金、工事までの流れを解説

日本は地震大国であり、どこに住んでいても心配はつきません。
近年、あちらこちらで地震が起きており、「我が家は大丈夫だろうか」と不安を抱えている人もいるでしょう。
築年数の経った住宅や古い構造、劣化など、耐震リフォームが必要な可能性もあります。
耐震診断を行うことで、必要性は明らかになりますが、その前にご自身でも診断チェックできる7つの項目を紹介します。
他にも、施工内容や費用、補助金についても解説しているので、リフォームの参考にしてください。
目次
耐震補強リフォームとは

耐震リフォームとは、既存住宅の耐震性能を向上する補強工事のことです。
地震による倒壊や損傷を防ぎ、家族や資産を守ることを目的とします。
たとえば、旧耐震基準で建てられた住宅は耐震性が低いため、耐震リフォームが必要となることが多いです。
また耐震リフォームは、大きく分けて3つの種類があるので、それぞれの特徴を紹介します。
耐震
耐震(たいしん)とは、地震対策の基本とされており、揺れに耐え、倒壊を防ぐ方法のことです。
耐力壁を増やしたり、柱や梁を太くしたり、筋交いを入れることで大地震への備えができます。
しかし、地震の揺れが住宅に直接伝わるため、建物の倒壊は防げても家具や食器などの倒壊、落下は避けられません。
また繰り返し地震が起きるとダメージが蓄積されるため、耐震構造を維持するためにメンテナンスは必要です。
制震
制震(せいしん)とは、地震などによる揺れを吸収する制振装置を設置して対策することです。
耐震と揺れ方はさほど変わらず、施工の目的も同じですが、2つの違いは対策方法です。
耐震は揺れに耐える一方で、制震は制振装置いわゆるダンパーが、揺れを吸収する構造になっています。
耐震構造と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。
免震
免震(めんしん)とは、建物と地盤の間に免震装置を設置して対策することです。
建物と地盤を離すことで、地震の揺れが建物に直接伝わらないため倒壊・損傷が抑えられたり、地震後の建物の機能を維持できたりします。
ただし、3つの中でコストが一番高額になるかもしれないのがデメリットです。
耐震補強は意味がない?
耐震補強は、建物を守るために重要な対策ですが、一方で「意味がない」と言われることがあります。
それは、効果が実感しにくいことや、それなりに費用もかかることがあげられます。
また想定外の地震には対応できないかもしれませんが、想定内の地震にはしっかり耐え、避難する時間を確保できるのは有効と言えるでしょう。
意味がないと言われる理由を払拭するには、適切な業者に耐震診断や補強設計、工事を依頼することが大切です。
自分でできる耐震チェック

既存住宅の耐震状況は見た目だけではわかりません。
セルフチェックできる7つの項目を順に解説するので、当てはまるものがあれば要注意です!
プロによる耐震診断をおすすめします。
1981年〜2000年に建築した住宅
建築基準は、大きな地震が起きる度に見直されてます。
既存住宅の建築時期によっては、耐震性能が不十分の可能性があるため以下の年数を参考に耐震診断を検討しましょう。
| 1950年建築基準法制定(1981年5月以前の建築建物が対象) | 旧耐震基準の住宅・地震対策の設計をされていない・大地震で倒壊の可能性大 |
| 1981年建築基準法制定(2000年5月以前の建築建物が対象) | 新耐震基準の住宅・耐力壁が大幅に増加している・2000年以降の新基準は満たしていない |
| 2000年建築基準法制定(2000年6月以降の建築建物が対象) | 現行耐震基準の住宅・基礎、壁、柱の対策がされている・概ね問題はなし |
※耐震性能は、建物によるため必ずしも倒壊しないということではありません。
シロアリが発生している
シロアリ被害は、住宅の構造部分を腐食・空洞化させ深刻な損傷を与えます。
柱や梁、床などの木材を食べるため、建物の強度低下や地震などの災害リスクを高める要因にもなるでしょう。
とくに木造住宅のシロアリ被害は、より深刻なため早期発見・早期対処が必要です。
耐震性の維持・向上のためにも、定期的にシロアリ防除や予防を行いましょう。
家の揺れを感じやすい
建物に揺れを感じる瞬間は地震だけではありません。
大きな車が通ったり、強風だったりが原因で揺れを感じるのであれば、建物の構造や地盤、老朽化が疑われます。
耐震強度を評価する耐震診断を受けて、リフォームが必要か早急に確認しましょう。
1階がガレージ、壁が少ない構造
1階にガレージを設けると、大きな開口部が必要になります。
そうすると家を支える壁や柱が少なくなり、構造的な強度が低下しやすいのです。
とくに2階建であれば、1階の耐震強度の低下により家全体に影響を及ぼす可能性があります。
同様の理由から吹き抜け・狭小住宅も不安が残ります。
ただし、適切な計画や強度のある素材、柱や梁を太くするなどの対策をとっていれば問題ありません。
増築を2回以上実施している
耐震の強度に、耐力壁の数が深く関わります。
元の建物にはしっかり耐震補強されていても、増築した部分の床面積に耐力壁が少ないかもしれません。
増築工事の際に建築確認などの手続きを行ったのであれば、問題ないですが、省略していたり、工事にて柱や梁を抜いたりしたのであれば十分注意が必要です。
また、増築を繰り返している場合、構造が不明瞭になっている可能性があります。
現状を把握するためにも、耐震診断を行いましょう。
過去に災害被害に遭ったことがある
これまでに浸水・火災・大震災の被害経験がある場合は注意が必要です。
| 浸水 | ・木材の腐食 ・鉄骨の錆び ・基礎の劣化 |
| 火災 | ・鉄骨の劣化、変形、強度低下 ・コンクリートの劣化、変形・消化活動による木材の劣化 |
| 大地震 | ・ダメージが蓄積 ・旧耐震基準の建物 ・想定外の劣化や亀裂 |
これらの震災経験がある建物は、将来的な地震に対する抵抗力が弱まっている可能性があります。
基礎や土台部分の強度が低下することで、家全体の構造が不安定になったり、寿命が短くなったりと万が一に備える必要があるのです。
建物の安全性を確保するために、耐震診断を行っておきましょう。
壁の配置バランスが悪い
壁の配置バランスが悪いと、地震の揺れによる『ねじれる力』に耐えられず倒壊する恐れがあります。
| ・開口部が片側に集中している ・窓が建物の角に設けられている ・南側にバルコニーやリビングなど広い間取り ・北側に玄関や風呂、キッチンなど細かく仕切った間取り …など |
よくある間取りを思われますが、全体として必要な壁の量が満たされていても、どちらか一方に偏りがある場合は、大きな地震の強い揺れで、ねじれて倒れてしまいます。
ただし、建築基準法で定められた耐震基準をクリアした設計であれば問題はありません。
少しでも耐震性に不安がある場合は、耐震診断を行うことをおすすめします。
耐震リフォーム費用の目安

耐震リフォームは、工事内容によって大きく異なります。
そのため、およその金額にはなりますが150万円程度と言われており、大掛かりな工事になると300万円を超えることも珍しくありません。
一方、耐震診断はおよそ20万円〜30万円程度で、築年数・建物の状態・構造によって変動します。
ただ、耐震診断や耐震リフォームの内容によっては、補助金制度を利用できることがあるので、以下の記事を参考にしたり、リフォーム会社に相談したりして納得の住宅に生まれ変わらせましょう。
【2025年】住宅リフォーム支援制度一覧!申請方法・補助金額・注意点を解説
耐震リフォームの内容・流れ

耐震リフォームを決定する前に、現地調査と耐震診断を行います。
その結果に応じて、工事プランの提案、工事へと進みます。
1.現地調査・耐震診断
まずは、住まいの耐震性や劣化状況を専門業者が現地調査します。
| ・目視調査(壁、柱、基礎、屋根など) ・床下や天井裏の調査 ・間取り、筋かいの確認 ・建材の強度確認 ・設計図面の確認(ない場合は描き起こし) …など |
上記の調査や確認の結果をもとに、耐震性能の評価や補強の必要性を判断します。
2.プラン・見積もり
耐震診断の結果をもとに、不十分だと判断した場合、補強工事プランや見積もりを作成し、提案します。
もし、希望のリフォームがあればこのタイミングに伝えましょう。
予算・要望・耐震性能の補強などを加味して、工事内容を決定します。
3.工事
耐震リフォームには、主に壁の補強、基礎の補強、屋根の軽量化、接合金具の設置があります。
| 壁の補強 | 外壁やクロスの下地に耐震壁を設置して耐震性を高める |
| 基礎の補強 | 基礎を打ち増しやひび割れを補強して、強度を上げる |
| 屋根の軽量化 | 屋根素材を軽いものに替えて、耐震性を上げる |
| 接合金具の設置 | 土台や柱に耐震金具を設置して、強度を補強する |
耐震補強工事の内容や規模によっては、住みながらでも工事が可能です。
ただし、大規模のリフォーム工事になると、仮住まいが必要となり、それなりに期間もかかります。
室内のものを撤去(移動)することも考慮して、工事開始日を相談しましょう。
耐震リフォームに適応した補助金

耐震リフォームに活用できる補助金制度は、主に自治体が運営しているものばかりです。
地域によって補助金制度の補助要件や補助金額、工事施工者の条件などが異なるため、お住まいの自治体や公式ホームページにて詳細を確認しましょう。
ここでは、一部地域の補助金制度を例にて紹介します。
| <東京都墨田区:耐震リフォーム補助金制度> |
| ①木造住宅耐震改修促進助成事業 ◆補助要件 ・旧耐震基準、新耐震基準の木造住宅が対象 ・耐震診断にて耐震性が不足すると判断された木造住宅 ◆補助金額 ・耐震改修工事費用に対して、費用の5分の4(上限120万円) ・耐震改修設計費用に対して、費用の3分の2(上限20万円) ◆工事施工者の条件 ・とくになし 参考元:東京都墨田区HP「木造住宅耐震改修促進助成事業(耐震改修工事)」 |
| <愛知県名古屋市:耐震リフォーム補助金制度> |
| ①木造住宅耐震改修助成 ◆補助要件 ・耐震診断の結果、判定値が1.0未満の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された、2階建て以下の木造住宅(戸建て、長屋、共同住宅) ・住宅以外の用途に使用している延べ面積の2分の1未満の住宅 ◆補助金額 ・一般世帯最大115万円(1住戸当たり) ・非課税世帯最大165万円(1住戸当たり) ◆工事施工者の条件 ・とくになし 参考元:愛知県名古屋市HP「木造住宅耐震改修助成」 |
| ②非木造住宅耐震改修助成 ◆補助要件 ・昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅のうち耐震診断にて「構造が不十分」と判断された住宅 ◆補助金額 ・戸建て:耐震改修工事の約23%(60万円) ・共同住宅、長屋:耐震改修工事の約23%(30万円×住戸数) ・マンション:耐震改修工事の3分の1(50万円×住戸数) ◆工事施工者の条件 ・とくになし 参考元:愛知県名古屋市HP「非木造住宅耐震改修助成」 |
| <大阪府堺市:耐震リフォーム補助金制度> |
| 住宅(マンションを除く。)の耐震改修補助 ◆補助要件 ・昭和56年5月以前に着手した住宅 ・建築基準法42条の道路に接道している住宅 ◆補助金額 ・木造:工事費用の3分の2(80万円〜100万円) ・非木造:工事費用の3分の2(80万円〜100万円) ・シェルター設置:工事費用の3分の2(30万円) ◆工事施工者の条件 ・とくになし 参考元:大阪府堺市HP「住宅の耐震改修補助内容」 |
耐震診断に適応した補助金
耐震診断の費用は、規模によって異なりますが木造住宅であれば、およそ5万円〜40万円。
鉄骨造やRC造では1m2あたり1,000円から3,000円程度が目安です。
しかし、建物の状態や図面の有無、業者によって費用は変動するので、必ず相見積もりをとってから依頼先を決めましょう。
また耐震リフォーム同様に、耐震診断にも活用できる補助金制度が自治体にて準備されています。
各自治体によって補助要件や補助金額などが異なるので、こちらも自治体や公式ホームページにて詳細を確認するようにしてください。
たとえば、東京都台東区の場合「木造住宅/上限20万円以内」「木造住宅以外の住宅/上限50万円以内」「住宅以外の建築物/上限20万円以内」と定められています。
一方、名古屋市では無料で耐震診断が実施されているため、お住まいの方は利用してみましょう。
参考元:東京都台東区HP「耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成」
耐震診断の申込み流れ
| 1.お住まいの自治体に問い合わせ 2.必要書類を準備 3.窓口にて提出 4.耐震診断を実施(およそ2週間程度) 5.耐震診断の結果報告(およそ1ヶ月程度) |
一般的に必要書類は、申込書・登記簿謄本・登記事項証明書・建物の平面図や付近見取図・
診断費用の見積書・診断士の資格証明書類(共同住宅の場合は、入居者の同意書)などがあげられます。
書類を準備する前に、必ずお住まいの自治体に耐震診断の補助制度が導入されているか確認してください。
地域によっては、準備がないところもあります。
まとめ

日本に居住している以上、地震の心配は続きます。
震災時に大切な家(建物)、命を守るためにも耐震性はとても重要です。
耐震診断や耐震リフォーム工事、それぞれにそれなりの費用はかかりますが、震災時の被害費用を考えると事前にできる対策をしていて損はありません。
国も耐震性の強化に注目しており、たくさんの補助金制度を設けています。
国からの補助と自治体からの補助を組み合わせることで、予算内でできる工事を検討してみましょう。
また、業者選びも大切です。
耐震診断の資格保有者が在籍していたり、実績・口コミを確認したりして、3社以上の専門業者から見積もりを取りましょう。
比較・検討し、お任せできる担当者に依頼してくださいね。